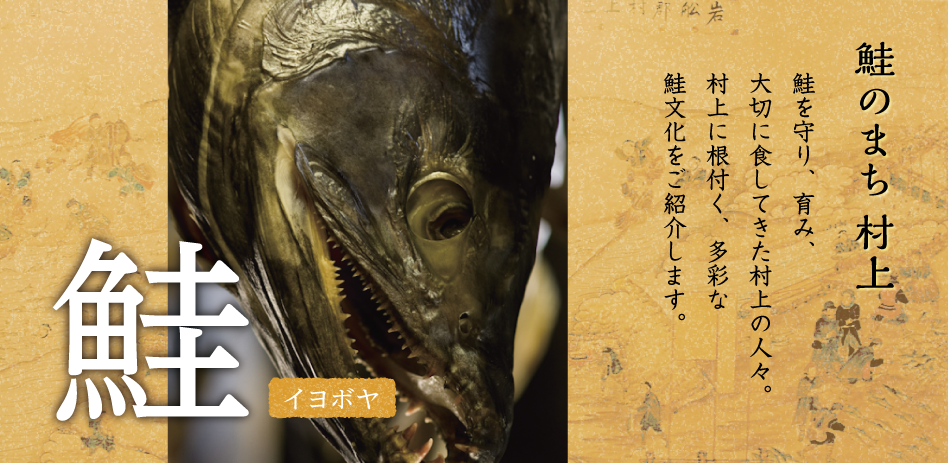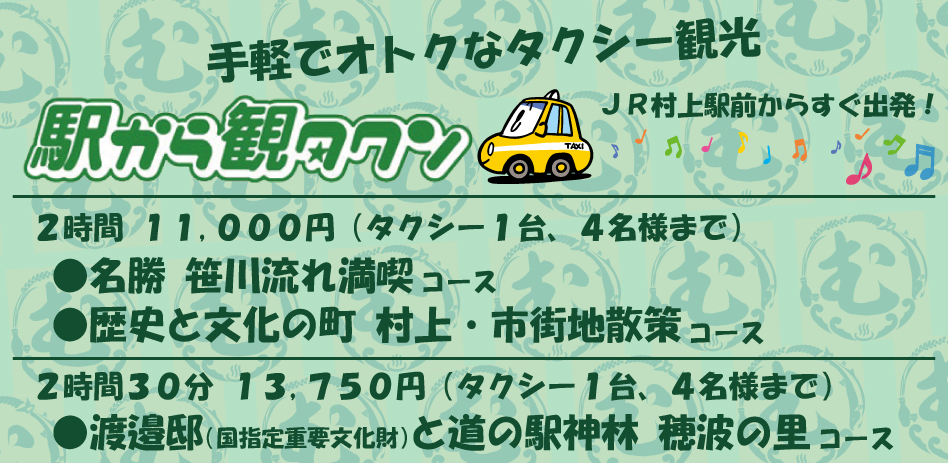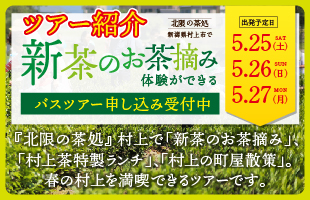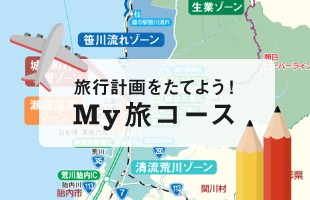注目! 村上の“旬”レポート 村上市の旬な情報・話題を隊員たちが報告します!もっと見る
-
イヨボヤ小ネタ帳 2024/04/25
-
村上 四季の愉しみ 2024/04/20
-
城下町村上 春の庭 百景めぐり 2024/04/19
-
日本酒はお好きですか? 2024/04/15
イベント情報もっと見る
-
満開のしだれ桜の下でお花見をしながら、春を満喫しませんか?
期間中は、各種山菜・とち餅・あく笹巻き・笹団子などの地元特産品、軽食・飲み物、民芸品等の販売も行います。
▶花見会・大正琴演奏会
【日時】2024年4月28日(日)11:00~14:00
●先着順で豚汁無料サービス
●大正琴・文化琴演奏さきそう会 演奏(11:30~)
※いずれも雨天時は順延・中止の場合があります
▶花見弁当の予約販売
イベント期間中、豪華花見弁当(1,000円・税込)を予約販売します。
前日昼までにご注文をお願いします。会場にも配達します。
●菅原鮮魚店(TEL 0254-76-2657)
●増子商店(TEL 0254-76-2017) -
▶観覧料(常設展観覧料を含む)
大人400円・小中高生100円
※20名様以上の団体の場合は大人320円・小中高生80円
▶休館日
月曜日(月曜が祝日の場合は翌火曜休館)
▶共催
村上市教育委員会
-
村上どんぶり合戦の2024年 春・夏編がスタート! どんぶりを彩るさまざまな食材は、贅を極めたものから希少なものまで、ここ村上でしか食べられないものばかり。各店が趣向をこらした一杯を、この機会にどうぞお召し上がりください。
※営業時間や定休日は参加店ごとに異なります。直近の情報は各店舗へ直接お問い合わせください
▶石挽き蕎麦と和食処 悠流里[ゆるり]の夜営業休止について
石挽き蕎麦と和食処 悠流里(パンフレットMAP No.06)は、2024年4月から当面の間、夜の営業を休止します。
インフォメーションもっと見る
- 募集2024/04/25
- 募集2024/04/16
- 募集2024/04/05
- 募集2024/02/27
- 募集2024/01/04
- 募集2023/11/29
- 交通情報2023/09/21
- 募集2023/05/27
- 受賞(認定)2023/03/09
- 交通情報2021/03/08