くつわ団子【3月1日】

農作業が現在のように機械化されるまでは、ほとんどの仕事が人の力と牛馬の力で行われた。
農家の春仕事は、まず3月1日のくつわ団子の行事から始まった。「くつわ」とは、手綱をつけた馬の口にかませる轡[くつわ]のことである。
くつわ団子は、朝早くに餅米の粉を少々大きめの団子に丸め、大鍋のあんこ汁に入れて火にかけ、ゆるりと煮くるめる。この団子を神仏にお供えし、この年の豊作を祈った。


日ごと移ろう四季がある日本では、季節ごとの行事とそれに伴う食(行事食)が大切にされてきました。ここ新潟県村上市でも、四季折々の行事に加え、地域の祭りや神事等で供される当地ならではの食があり、それは「節がない」といわれる現代において、大切に受け継いでいきたい文化の一つでもあります。
当コンテンツは、村上商工会議所と食の街・むらかみブランド化事業委員会が手掛けた『越後むらかみ 食の聞き書』(2015年発行)の中から、ひと月に1~2編ずつ、行事と食に関するエッセイを掲載します。イラストは石田光和さん(エムプリント)です。
※地域や風習によって掲載されている内容とは違っている場合があります
くつわ団子【3月1日】

農作業が現在のように機械化されるまでは、ほとんどの仕事が人の力と牛馬の力で行われた。
農家の春仕事は、まず3月1日のくつわ団子の行事から始まった。「くつわ」とは、手綱をつけた馬の口にかませる轡[くつわ]のことである。
くつわ団子は、朝早くに餅米の粉を少々大きめの団子に丸め、大鍋のあんこ汁に入れて火にかけ、ゆるりと煮くるめる。この団子を神仏にお供えし、この年の豊作を祈った。
せつぶん
節分【2月3日頃】
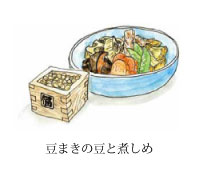
子どもたちの鬼成敗の声が響く。
夕方、囲炉裏端の灰の表面をさらい取り、塩をまいて清めてから豆木で火をたき付け、大豆をいって一升枡[いっしょうます]に入れる。主人が羽織袴で枡の豆を大神宮様に供え、家内安全・悪事災難をよけるよう拝み、神棚に向け「福は内」と大声で豆をまき、外に向かって「鬼は外」と豆を投げつける。茶の間、座敷と家中に豆をまき、土蔵にもまく。「目をつぶって歳の数だけ豆を拾うと福が授かる」と家内中、目隠しをして拾った。
干鰯*[ほしか]をヒイラギの枝に刺し、豆木に干鰯と昆布を下げて入り口に付け、家に入る鬼や魔物を避ける。鬼が逃げるとき、ヒイラギのとげで目を刺すのだという。まいた豆を集めて、天気占いや作占いも楽しんだ。
*脂肪を絞ったあとのイワシを干したもの。肥料にする
がんたんちょうしょく
元旦朝食【1月1日】
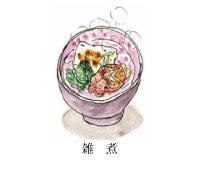
元旦は、神社参拝が終わると家中そろって朝食を食べる。御神酒をいただき、雑煮餅かあん餅を食べる。数の子・赤カブの甘酢漬け・鮭・大根汁。
2日早朝には、縁起物の「さくら飴」を8~13歳までの男の子が、重箱に小さな丸い淡い紅色と白色のあめを入れ、風呂敷に包んで各家に売り歩く。さくら飴は、お菓子屋から仕入れ、その利益で書き初めに使う筆や半紙などを買う、大事な商いの習い始めでもある。