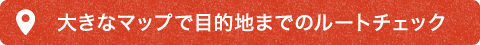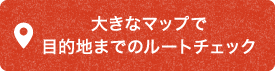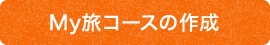石船神社[いわふね-じんじゃ]
「神様が天の石船[あま-の-いわふね]に乗りお出でになられた」との伝説をもつ磐舟郡総鎮守。圏域『岩船』という地名の由来となっています。創祀は大化4(648)年、磐舟柵設置以前と伝わり、御祭神は饒速日命[にぎはやひのみこと]。 大同2(807)年、北陸道観察使・秋篠朝臣安人が下向の際に社殿を建立。越後国の北の守護神として京都・貴船神社の御祭神三柱を合祀以来千二百年、「明神様」と称されて広く信仰を集めました。延喜式神名帳には越後磐船郡の筆頭に記載され、色部氏・本庄氏・歴代村上藩主等に鎮守の御社として篤い保護を受けます。明治期には越後一宮 彌彦神社に次ぐ県内最初の縣社に列しました。 【社叢】 石船神社の社叢は、天然ヤブツバキの群生地で県天然記念物(昭和33年指定)です。 【石碑・句碑】 境内には、磐船柵趾の碑と松尾芭蕉の句碑2基があります。 【石船神社と岩船大祭】 石船神社の例祭(10/18、19)が岩船大祭です。先太鼓と木遣りを先頭に、御舟屋台をはじめとした9基のしゃぎり屋台が共に御神幸します。岩船大祭と「ともやま行事」は県無形民俗文化財(昭和62年)に指定されています。