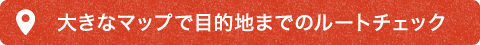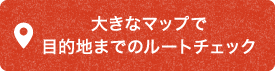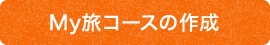村上城跡(お城山)
村上城は、標高135mの独立峰・臥牛山[がぎゅうさん]に築かれた城で、築城年代は不明ですが、16世紀前期には城が存在していたものと考えられます。戦国時代には本庄氏の本拠地として、永禄11(1568)年の上杉謙信との篭城戦など、幾度も戦いが繰り広げられました。江戸時代に入ると、村上氏・堀氏・松平氏らの城主によって城の改造と城下町の建設が行われ、村上城は北越後の中心拠点として整備されました。 山頂までの道は整備され、約20分ほどで登ることができます。村上のシンボルとして近隣住民はもちろん、観光客もたくさん訪れる名所です。 ≫ご注意ください ・ゴミ箱は設置されていません。出たゴミは必ずお持ち帰りください ・山頂(天守跡)に自動販売機やトイレはありません。自動販売機は登城口に、トイレはお城山児童公園をご利用ください ・音の出るもの(熊鈴・ラジオ等)を携行し、複数人で行動するなど、クマとの遭遇を避ける対策を行ってください