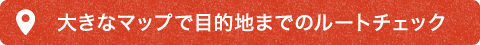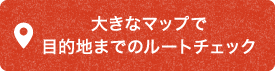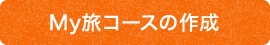村上市指定文化財 旧岩間家住宅
東西方向に棟を持つ直屋・寄棟造りの茅葺き住宅で、平成7(1995)年に現在地に移築復原されました。建設当初は連棟式の長屋形式の住宅であったものを、安政5(1858)年に一戸建の武家住宅に大改造しました。茅葺き屋根の梁間が二間と小さく、背面の増築した下屋根が大きいことでも伺い知ることができます。 【旧岩間家住宅の旧所在地】 旧岩間家住宅は、現在の新潟県村上市飯野2丁目にあったものを現在地に移築復原したものです。旧所在地は、江戸時代に五軒町と呼ばれていたところで、町人町(細工町)と接していました。明治初年の城下絵図によると、この岩間家の位置に「須貝勝太郎」と記されていることから、もとはこの村上藩士・須貝勝太郎の屋敷であったと推測されます。 なお、岩間氏の先祖は山形県の旧新庄藩の武士であったと伝えられており、この屋敷については昭和23年に取得し現在に至っていますが、住宅部分については村上市へ寄付されました。 また、この岩間家住宅は平成4年9月21日に村上市の有形文化財として指定されましたが、茅葺屋根等の破損と老朽化が激しく、一時的な補修では建物の維持が図れないということから、同年12月に、移築復原を前提とした解体と部材の保存格納が行われました。 (村上市郷土資料館) 【復原調査と安政5(1858)年の大改造】 この住宅の構造形式は「直屋[すごや]・寄棟造・茅葺・一戸建」であり、典型的な村上の武家住宅の形式であるといえますが、この住宅の特徴は、この建物が建設された当初の形態と安政5年に行われた大改造後の形態がまったく異なるものになったことです。 武家住宅というのは基本的には藩の官舎であり、身分や格式によって厳しい建築規制がありました。つまり、その武士の身分や格式によって住まいする住宅の規模や形式が決まっていたため、長屋形式の住宅に住まうのは下級武士であり、それに対して一戸建形式の住宅に住まうのは中級以上の武士でした。このことからも、こうした建物の形式そのものを変えるような改造は、よほどのことがない限り行われなかったのではないかと考えられます。 この改造が行われた時期については、改造によって取り払われた部材の痕跡を隠すために使用した「カブセ」という小部材の裏に、当時の大工が書いた「墨書[ぼくしょ]」が発見されたことによります。そこには「安政五戌年午歳五月吉日 大工 羽黒町清八造之」と記されていました。こうした職人による墨書や落書きによって建築年代や改造年代が判明することは珍しいことではありませんが、この場合の大工清八の墨書は、建設当初からのものではなく改造時のものであり、当初の建物が建設されたのは、おそらくもう50~60年前にさかのぼると思われます。 では、建設当初はどのような形態であったかというと、本来は2棟続きの《長屋形式》の住宅でした。そして、何か特別な事情が背景にあったのか、その2棟続きの長屋住宅の一方の材料を活用しながら、安政5年に《一戸建形式》に改造したものといえます。 (村上市郷土資料館)