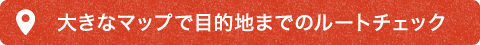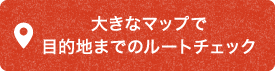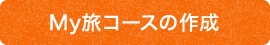【2025年営業中止】ゴールドパーク鳴海(鳴海金山)
【2025.04.22更新|2025(令和7)年度の営業中止について】 朝日スーパーラインが通行止めのため、2025(令和7)年度の営業を中止いたします。楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありませんが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 慶長年間には、全国の産金量の3分の1を産出したといわれている鳴海金山跡(黄金坑・大切坑)は、当時のタヌキ掘り(手掘り)の跡と荒々しい岩肌が残されたままになっています。千二百年の時を越え、現代によみがえった鳴海金山の姿をご覧ください。