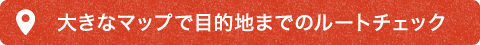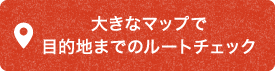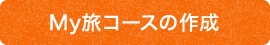稲荷山(番所山)
江戸時代、塩谷は村上城下と北国街道を結ぶ重要拠点であり、村上藩はこの山に番所を置いて、人や物の出入りを監視していました。そのため、番所山[ばんしょやま]と呼ばれていましたが、明治になり、廃藩とともに番所も廃されました。その後、お稲荷さんが祭られていることから「稲荷山」と呼ばれるようになりました。 山頂には三等三角点があり、国土地理院の2万5千分の1電子地形図にも「稲荷山」として掲載されており、新潟県で一番低い(標高15.3メートル)山です。37段の階段を上った山頂の展望台からは、塩谷のまち並みや日本海に浮かぶ粟島や佐渡、南西には弥彦山、角田山が海に浮かぶ島のように見えます。