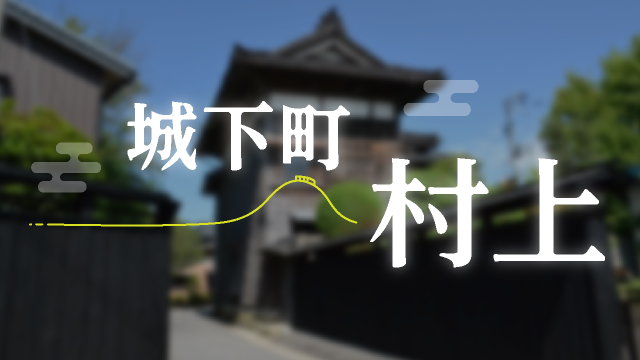江戸時代の村上藩は、藩主が目まぐるしく代わり、9家・21人の藩主が当地を治めました。
享保5(1720)年~明治4(1871)年までの151年間は内藤家の9人の藩主が治めました。先代藩主の父・信輝[のぶてる]が亡くなり、跡を取ったのは当時3歳だった信興です。
「江戸時代の村上 ~村上藩歴代藩主物語~」は、2023年11月3日~12月3日まで、おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)で開催された同名の展示を、おしゃぎり会館監修のもと、当サイト用に編集したものです。
おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)
https://www.sake3.com/spot/179

内藤信興【内藤紀伊守信興】
ないとう のぶおき
内藤信興は、信輝の次男として享保8(1723)年に江戸で生まれ、幼名を孫三郎といった。享保10(1725)年、父の卒去により3歳で家督を継ぐ。
元文元(1736)年12月に従五位下の紀伊守に叙任され、翌年に初入部。宝暦11(1761)年に長男・信旭[のぶあきら]に家督を譲るまでの36年間、藩主を務めた。
この間、元文3(1738)年には三面川[みおもてがわ]の鮭不漁による入札の取り止めを行ったほか、寛保2(1742)年に岩船の大火<173軒焼失>、翌3(1743)年には細工町の大火<24軒焼失>、寛延元(1748)年には再び岩船で大火<315軒焼失>、宝暦8(1758)年には久保多町からの出火による大火<116軒焼失>など、度重なる領地内の火災に見舞われている。
また、延享3(1746)年には、米価の急騰から、岩船・瀬波・村上の町人が塩谷の商人を襲った塩谷騒動なども起きた。

肴町のしゃぎり屋台
撮影日:2023年7月7日
宝暦10(1760)年には、内藤家の祖・信成[のぶなり]の150回忌を光徳寺で行い、城下の安寧と家運隆盛を祈願して、城下の要衝地に九品仏[くほんぶつ]の建立を行った。またこの年には、現存する村上大祭の屋台の中で、最も制作年代の古い肴町のしゃぎり屋台が作られた。
常照山法善院 光徳寺
https://www.sake3.com/spot/2451
九品仏(上品上生 善沢寺前)
https://www.sake3.com/spot/289
※この他に8体あります
村上大祭の屋台11~15番(鍛冶町・肴町・長井町・羽黒町・庄内町)
https://www.sake3.com/murakamitaisai/72
信興は安永9(1780)年、58歳で江戸で没した。