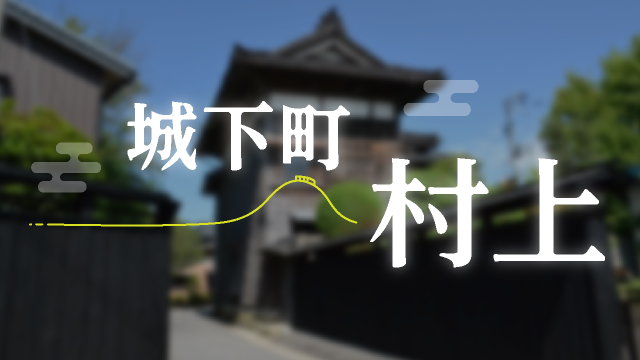江戸時代の村上藩は、藩主が目まぐるしく代わり、9家・21人の藩主が当地を治めました。
宝永元(1704)年~同7(1710)年の6年間を治めた本多家が三河国刈谷に転封となり、代わって村上へ入封してきたのは松平輝貞でした。松平家は宝永7(1710)年~享保2(1717)年の7年間を治めました。
「江戸時代の村上 ~村上藩歴代藩主物語~」は、2023年11月3日~12月3日まで、おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)で開催された同名の展示を、おしゃぎり会館監修のもと、当サイト用に編集したものです。
おしゃぎり会館(村上市郷土資料館)
https://www.sake3.com/spot/179

松平輝貞【松平右京太夫輝貞】
まつだいら てるさだ
松平輝貞は、「知恵伊豆」といわれた松平伊豆守信綱[のぶつな]の孫で、寛文5(1665)年に甲斐守輝綱[てるつな]の六男として生まれた。同12(1672)年に輝綱が没した後、その遺領の内から5千石が分け与えられた。
元禄元(1688)年には、中奥の小姓として江戸城に召し出され、翌年から5代将軍・綱吉の側近に仕え、右京亮[うきょうのすけ]に任ぜられた。同4(1691)年に叔父・信興[のぶおき]が死去したため、その家を継ぎ、遺領3万2千石を。翌年2月には下野国壬生城をたまわり、次の年には綱吉の側近に勤仕を命ぜられた。
元禄7(1694)年、従四位下・右京太夫に昇叙。同8(1695)年には上野国高崎城に移され5万2千石と進み、その後は二度の加増があり、宝永元(1704)年には7万2千石となった。これは綱吉からの信任が厚かったためで、輝貞は柳沢吉保[やなぎさわよしやす]とともに綱吉の側近を務めた。
宝永6(1709)年に綱吉が亡くなると、家宣[いえのぶ]が6代将軍になり、輝貞と吉保はともに幕府の中枢から離れ、翌年に高崎城は家宣の側近・間部詮房[まなべあきふさ]がたまわり、輝貞は村上城へ移された。
享保元(1716)年、7代将軍・家継[いえつぐ]が8歳で没すると、家宣・家継と2代にわたり側近だった詮房は退き、翌年には村上城へ移され、輝貞は再び高崎城へ移ることになった。
輝貞の村上在城は7年ほどで、石高は本多忠隆の頃の5万石から7万2千石と増えたものの、城下では侍屋敷や組屋敷に空き家が多くあり、榊原氏時代(1667-1704)に召し上げられた駒込一番町から四番町までは長屋を取り壊し、町人などに売却されて茶畑などに変化していった。
輝貞は、享保15(1730)年に老中格となり、15年余もその職にあり、延享4(1747)年に83歳で没した。輝貞後の松平氏は大河内氏と称し、幕末まで高崎に在城した。