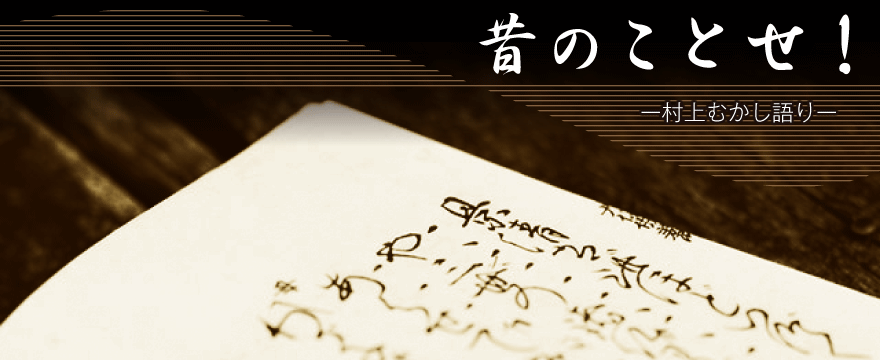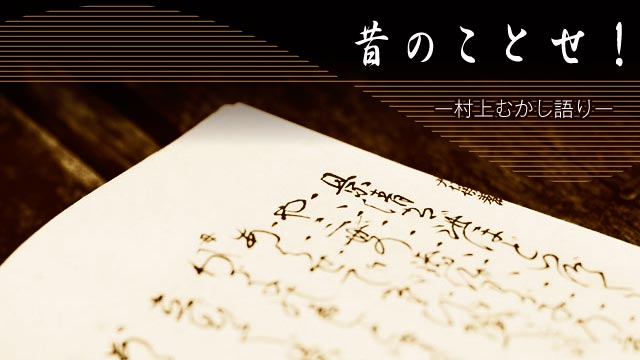膠着した戦局を打開するため、味方の諸将から人質を差し出させて引き締めをはかり、軍励することは、総大将の常套手段である。
敵をば武力をもちいて屈服させ、家臣や味方には武断政治で服従させる。いわゆる暴政である。仁愛を基とする主従関係ではない。本庄家の統治は、
「臣として主に仕える道は愛をもととして敬を守り礼儀を忘るへからず候」『文和二年諸〆務方申渡書』愛とは、仁である。仁は人の道、愛は恋愛的な愛とは別で人道である。単なる武断によって強固な家臣団を形成するのではなく、より高度な仁道をもって忠誠心を涵養しようとしたのであった。本庄家は輝虎より以前に、このような儒教的な文言をもりこんだ家中法度を示している。この徳育は誰が奨励したのか解らないが、この方針が結束を強くし、越後随一の軍団を育てたと考えてもよいか。
とまれ籠城して耐えること一年、上杉兵は攻め倦(あぐ)む。その間、本荘へは、武田方の密使が上杉の警戒網を抜けて接近したり、下渡山城あるいは藤懸城の争奪があったりするが大局を変えるほどの勝敗ではなかった。
籠城は春以来で、武田信玄ほか、葦名も本庄を後援しまた信玄に応じた越中の勝興寺(しょうこうじ)は、椎名康胤(しいなやすたね)を後援して上郡に攻め入るようすを見せる。また国人衆では石塚玄蕃の離反もあり、その正月早々には、どこの領主か不明ながら本庄への支援として一千名も到着するという情報も入った。
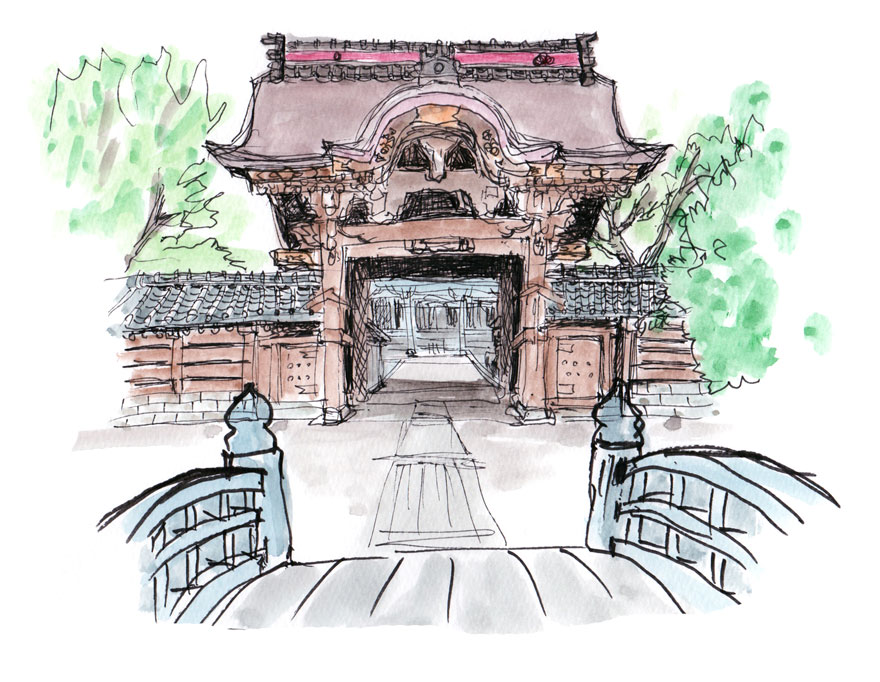
上杉軍による城攻めの進捗は、果たしてどうか、外郭を攻め根小屋を焼き、木戸を閉鎖したりはしたが、山上の郭が攻め破られたようすはない。がしかし、武田の支援軍は途中、上杉方に遮られているし、伊達も葦名も積極的に支援隊を送ってくるようすはない。
籠城戦の勝敗は外部からの支援の有無にかかっている。伊達と葦名が肩を入れるのは、本庄であるが、武田と同じく間接的なものである。いや武田より腰が引けた関与である。
輝虎陣営は統率がとれなく、諸将は戦意に欠ける。繁長陣営は地の利を得た城と忠節の厚い将兵が守っているが孤軍である。つまり攻守ともに短所がある。その短所が、和議を結ぶ要素となる。
大場喜代司
『村上商工会議所ニュース』(2016年2月号掲載)村上市史異聞 より
『村上商工会議所ニュース』(2016年2月号掲載)村上市史異聞 より